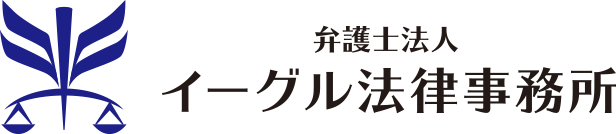1 はじめに
相続法が改正され,新たに特別寄与料の請求の規定が設けられました。
今回は,特別寄与料の請求権者について簡単にご説明します。
2 「被相続人の親族」に限定した経緯
法は,特別寄与料の請求権者を「被相続人の親族」としました(民法1050条1項)。
改正の議論の際は,被相続人の長男の奥さんを想定して議論していました。
しかし,条文にそれを明記してしまうとが,法が一般市民に対し「長男の奥さんが夫の両親の介護をするべきである」という価値判断(メッセージ)を示すことになりかねません。
そこで,法は,特別寄与料の請求権者を,「被相続人の親族」に限定することになりました。
3 事実上の養子も請求権者になる
「被相続人の親族」には,被相続人と養子縁組をしていない配偶者の連れ子も含まれます。
よって,いわゆる事実上の養子も,特別寄与料を請求できます。
4 内縁配偶者は請求権者とならない
もっとも,内縁の配偶者は「被相続人の親族」ではないので,特別寄与料の請求をすることは出来ません。
ちなみに,改正の議論の際,内縁の配偶者も請求権者に含めるべきであるとする見解もあったようです。
しかし,内縁の配偶者は幅の広い概念であり,事実認定が難しいため,見送られることになりました。
そうすると,内縁配偶者が特別寄与料に相当する請求をしょうと思えば,準委任契約,事務管理,不当利得の規定に基づき,相続人に請求していくことになります。そのハードルは高いと言わざるを得ないでしょう。
5 最後に
以上,特別寄与料の請求権者についてご説明しました。
相続問題でお困りの方はイーグル法律事務所までご相談ください。