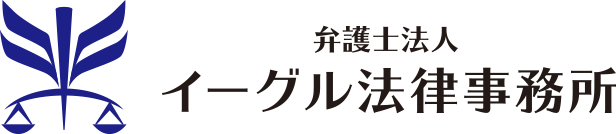遺留分減殺請求⇒遺留分侵害額請求
 1 具体例
1 具体例
経営者であった太郎さんは,会社の土地建物(評価額1億1123万円)を長男二郎さんに、預貯金(1234万5678円)を長女サクラさんに相続させる旨の遺言を残して,亡くなりました。
この場合,長女サクラさんの遺留分侵害額は1854万8242円となります。
2 呼び方の変更について
サクラさんは遺言の内容に不満を持ち、遺言によって生じた権利関係を是正したいとします。この場合、改正前、サクラさんは「遺留分減殺請求」をすることになりました。もっとも、改正後は「遺留分侵害額請求」に名称が変更されました。
3 遺留分減殺請求(改正前)の内容
遺留分権利者が,遺留分に関する権利を行使すると,遺留分を侵害する部分が当然に無効となり,無効とされた部分に相当する権利が遺留分権利者に移転します。
先の例では、サクラさんが次郎さんに対して遺留分減殺請求をしたとします。そうすると、会社の土地建物は、太郎さんが9268万1758/1億1123万、サクラさんが1854万8242/1億1123万の持分割合で共有することになります。
遺言による権利移転を一部無効にするという意味で「減殺」という文言を使うことにした関係で、「遺留分減殺請求」とされたのです。
4 遺留分減殺請求の問題点
例えば,太郎さんはもともと事業家でしたが,遺産である不動産のほとんどが事業用の不動産であったとします。
そして,太郎さんは,長男二郎さんに事業を承継して欲しいとの思いから,上述の遺言を作成したとします。
この場合,サクラさんが長男二郎さんに対し遺留分減殺請求をすれば,事業用の不動産について,二郎さんが4分の3,サクラさんが4分の1の割合で共有することになります。
そのため,二郎さんが事業経営が悪くなってきたので事業用不動産を売却してその代金を運転資金にしようとしても,サクラさんの共有持分4分の1がネックとなり,円滑に不動産を売却することが出来ない可能性があります。
5 遺留分に関する権利の金銭債権化
そもそも,遺留分制度は,サクラさんのような遺留分権利者の生活保障などを目的とする制度です。この目的を達成するためには,遺留分権利者にその侵害額に相当する金銭を返還させることで十分といえます。
そこで,改正法では,遺留分を侵害する遺言による権利移転の効力は維持したうえで(遺留分無侵害の原因となった遺贈や贈与の効力は有効としたうえで),遺留分権利者に遺留分侵害額に相当する金銭債権が発生することにしたのです(民法第1046条第1項)。
6 遺留分侵害額請求と名称変更した理由
上述したとおり,改正前において遺留分に関する権利が遺留分減殺請求と呼ばれたのは,その権利行使により遺言による権利移転が一部無効になるからでした。
ところが,改正後は,遺留分に関する権利を行使しても,遺言による権利移転は無効とはなりません。つまり権利移転は維持されます。
そのため,遺留分減殺請求の「減殺」という文言は実態に合わなくなりました。
そこで,遺留分減殺請求は「遺留分侵害額請求」と改められることになりました。
7 最後に
以上,遺留分侵害額請求についてご説明しました。
遺留分に関連してお困りの方はイーグル法律事務所にご相談ください。